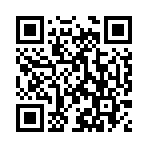スポンサーリンク
2009年04月25日
畑作り
今日はよく降りましたね。
これは昨日の情景。
森のレストラン横の枝垂桜、もう散り始めたかな、と思って見ていたら、
横の畑でうごめく人たちが


畑作りを始めたスタッフでーす

畝もこさえました。
今年はいのししの襲撃に負けず
おいしい野菜をたくさんつくりたいです
これは昨日の情景。
森のレストラン横の枝垂桜、もう散り始めたかな、と思って見ていたら、
横の畑でうごめく人たちが


畑作りを始めたスタッフでーす


畝もこさえました。
今年はいのししの襲撃に負けず
おいしい野菜をたくさんつくりたいです
Posted by もりのしぜんがっこう at
◆2009年04月25日21:31
│レストラン
2009年04月17日
カタクリ
誰もが知る 春の妖精 です。
日本産はピンクが一般的ですが、最近ではアメリカやカナダの黄花カタクリや白花カタクリもみられるようになりました。

オークヒルズの、森のレストラン横の山の斜面では、黄色カタクリが毎年、春の訪れを告げてくれます。

さて、植物はその生育地をひろげんがため、驚くべく秘策を出してきます。
カタクリはエライオソームという蟻が好む物質を種子につけ、蟻を媒体に生育地を広げるそうな。
甘いのかな?
今年、種子ができたら、舐めてみなくちゃ。
昔はこの鱗茎から片栗粉を作っていたというのは、ご周知の通りですが、葉も花も食べることができます。
花は可愛く、しかも食べられるとあれば、採って食べちゃいたいのは人の常。乱獲は免れなかったのでしょう。
かつてカタクリは、日本各地の落葉広葉樹林の林床で見ることができましたが、他のスプリング・エフェメラル同様、自生地が減少傾向にあります。
最近では、野山に人工的に植え、観光名所としているところもあります。
漫画王国で有名な飛騨市宮川の白木ヶ峰スキー場もそのひとつ。
今が見ごろをむかえています。
自生していたものを20万株に増やして整備したそうです。
見ごたえありそうですね。
週末は天気もよさそうなので、ちょっと足を伸ばすのもいいかも。

41号線をビューンと走って ( 法定速度はまもりましょう ) 、
古川町の卯の花街道の新緑の中をとおりぬけ、
森林浴で体もリフレッシュ。
おなかもすいて、そろそろランチと思ったら
そこは清見町。
森のレストランもすぐそこです。
日本産はピンクが一般的ですが、最近ではアメリカやカナダの黄花カタクリや白花カタクリもみられるようになりました。

オークヒルズの、森のレストラン横の山の斜面では、黄色カタクリが毎年、春の訪れを告げてくれます。

さて、植物はその生育地をひろげんがため、驚くべく秘策を出してきます。
カタクリはエライオソームという蟻が好む物質を種子につけ、蟻を媒体に生育地を広げるそうな。
甘いのかな?
今年、種子ができたら、舐めてみなくちゃ。
昔はこの鱗茎から片栗粉を作っていたというのは、ご周知の通りですが、葉も花も食べることができます。
花は可愛く、しかも食べられるとあれば、採って食べちゃいたいのは人の常。乱獲は免れなかったのでしょう。
かつてカタクリは、日本各地の落葉広葉樹林の林床で見ることができましたが、他のスプリング・エフェメラル同様、自生地が減少傾向にあります。
最近では、野山に人工的に植え、観光名所としているところもあります。
漫画王国で有名な飛騨市宮川の白木ヶ峰スキー場もそのひとつ。
今が見ごろをむかえています。
自生していたものを20万株に増やして整備したそうです。
見ごたえありそうですね。
週末は天気もよさそうなので、ちょっと足を伸ばすのもいいかも。

41号線をビューンと走って ( 法定速度はまもりましょう ) 、
古川町の卯の花街道の新緑の中をとおりぬけ、
森林浴で体もリフレッシュ。
おなかもすいて、そろそろランチと思ったら
そこは清見町。
森のレストランもすぐそこです。
Posted by もりのしぜんがっこう at
◆2009年04月17日14:25
│自然
2009年04月15日
「そこら辺に咲いとる白い花」、その名は?
飛騨に来て、初めて、この花の群生に遭遇した時、気分はすっかりアルプスの少女ハイジ。
ペーター、ユキちゃーんと叫んでで走りたくなる光景でした。

ところで、この花はなんぞや?と、親しくしている方にお伺いしたところ
「あ~そりゃ、そこらへんに、よく咲いとる白い花、やな。」
経済植物のスペシャリストだからといって野辺の花もスペシャリストとは限らないので、
これはいたしかたない。
後日、「そこら辺に咲いとる白い花」は別名「アズマイチゲ」と判明。
東の一輪草から、 東一華(アズマイチゲ)とのこと。
この花もまた、スプリング・エファメラルです。

アズマイチゲは明るくなると花が開き、
暗くなると閉じます。
その花は開いても、閉じても繊細で可憐。

さて、かつての「そこら辺に咲いとる白い花」は、宅地化が進んだり、天災にあったり、道路ができたりで「昔はよくそこらへんに咲いとったが、今では探さんと見られない花」となり、私に「そこら辺に咲いとる白い花」と教えてくださった御老体は、道の駅で、自分の作った大根の値段より高い値段の「そこら辺に咲いとる白い花」にどうしても納得がいかないご様子です。
今でも、意識して探していると、おや、こんなところに!というところで見ることができます。
是非、春の宝探しをやってみてください。
どうしても探せなかった方は森のレストランの玄関前にも咲いておりますので、見に来てください。
早く来ていただかないと、そろそろ、見ごろを逃してしまいますが・・・。
ペーター、ユキちゃーんと叫んでで走りたくなる光景でした。

ところで、この花はなんぞや?と、親しくしている方にお伺いしたところ
「あ~そりゃ、そこらへんに、よく咲いとる白い花、やな。」
経済植物のスペシャリストだからといって野辺の花もスペシャリストとは限らないので、
これはいたしかたない。
後日、「そこら辺に咲いとる白い花」は別名「アズマイチゲ」と判明。
東の一輪草から、 東一華(アズマイチゲ)とのこと。
この花もまた、スプリング・エファメラルです。

アズマイチゲは明るくなると花が開き、
暗くなると閉じます。
その花は開いても、閉じても繊細で可憐。

さて、かつての「そこら辺に咲いとる白い花」は、宅地化が進んだり、天災にあったり、道路ができたりで「昔はよくそこらへんに咲いとったが、今では探さんと見られない花」となり、私に「そこら辺に咲いとる白い花」と教えてくださった御老体は、道の駅で、自分の作った大根の値段より高い値段の「そこら辺に咲いとる白い花」にどうしても納得がいかないご様子です。
今でも、意識して探していると、おや、こんなところに!というところで見ることができます。
是非、春の宝探しをやってみてください。
どうしても探せなかった方は森のレストランの玄関前にも咲いておりますので、見に来てください。
早く来ていただかないと、そろそろ、見ごろを逃してしまいますが・・・。
Posted by もりのしぜんがっこう at
◆2009年04月15日18:47
│自然
2009年04月15日
福寿草
カタクリとともに春を告げる代表花です。
新春を祝う意味を持つ福寿草。和名を見ただけで、古来から人々がいかに春を待ち望んでいたかがうかがい知れます。
別名 元日草(がんじつそう) 朔日草(ついたちそう)こんな風な花の名前を見ると、本当に日本語って美しい、日本人って心が細やかだと、そう思います。
風まだ冷たいこの時期、この艶やかな花に出会ったら誰でも幸福な気持ちになるでしょう。
なので、花言葉は、「幸福をまねく」。

福寿草の花形は典型的なハナアブ型。その花の上で思う存分蜜をすい、遊べるよう平たい皿状をしています。黄色い花色はまだ他の花が咲いていない時期、私はここよ、見つけてよ、とハナアブに猛烈アピールしているわけです。さて、この猛烈アピールにノックダウンされたのはハナアブのみならず、江戸時代から多くの人々がこの花に魅せられ、多くの園芸品種が生まれたのでした。
他ならぬ私もその一人。黄色の福寿草とともに緋色の福寿草を育てております。
昨年の春はきれいなオレンジ色に染まっておりましたが、今年の花色はかぎりなく、黄色に近い花。なぜに?

とある本によりますと、寒さにさらすほど花は緋色を増すとのこと。なるほど、今年は確かに暖冬でした。
とすると、このまま温暖化が進むと、私の福寿草、全て黄色になる日も近いかも・・・・。STOP THE 温暖化!!
温暖化を阻止せねばと真剣に思った春でした。

こんなに多くの人に愛でられている福寿草ですが、その牛蒡のごとき根にはアドニンという強い毒成分を含みます。強心作用・利尿作用があり、民間薬として使われていますが、素人療法は中毒症状のみならず死に至る危険性があります。静かな山菜ブームのなか、くれぐれも誤飲にご注意ください。
清見町の西光寺では、いま福寿草の見ごろを迎えています。4月末ころまで楽しめるとのことです。
新春を祝う意味を持つ福寿草。和名を見ただけで、古来から人々がいかに春を待ち望んでいたかがうかがい知れます。
別名 元日草(がんじつそう) 朔日草(ついたちそう)こんな風な花の名前を見ると、本当に日本語って美しい、日本人って心が細やかだと、そう思います。
風まだ冷たいこの時期、この艶やかな花に出会ったら誰でも幸福な気持ちになるでしょう。
なので、花言葉は、「幸福をまねく」。

福寿草の花形は典型的なハナアブ型。その花の上で思う存分蜜をすい、遊べるよう平たい皿状をしています。黄色い花色はまだ他の花が咲いていない時期、私はここよ、見つけてよ、とハナアブに猛烈アピールしているわけです。さて、この猛烈アピールにノックダウンされたのはハナアブのみならず、江戸時代から多くの人々がこの花に魅せられ、多くの園芸品種が生まれたのでした。
他ならぬ私もその一人。黄色の福寿草とともに緋色の福寿草を育てております。
昨年の春はきれいなオレンジ色に染まっておりましたが、今年の花色はかぎりなく、黄色に近い花。なぜに?

とある本によりますと、寒さにさらすほど花は緋色を増すとのこと。なるほど、今年は確かに暖冬でした。
とすると、このまま温暖化が進むと、私の福寿草、全て黄色になる日も近いかも・・・・。STOP THE 温暖化!!
温暖化を阻止せねばと真剣に思った春でした。

こんなに多くの人に愛でられている福寿草ですが、その牛蒡のごとき根にはアドニンという強い毒成分を含みます。強心作用・利尿作用があり、民間薬として使われていますが、素人療法は中毒症状のみならず死に至る危険性があります。静かな山菜ブームのなか、くれぐれも誤飲にご注意ください。
清見町の西光寺では、いま福寿草の見ごろを迎えています。4月末ころまで楽しめるとのことです。
Posted by もりのしぜんがっこう at
◆2009年04月15日12:26
│自然
2009年04月14日
「春の儚いもの」たち
飛騨の春は短く、短い春を謳歌するかのように、一斉に多くの花が咲き競います。
まさに、百花繚乱。心躍る季節です。

さて、それらの花の中で、春まだ浅い頃顔を出し、早々に花を付け、種子をつけ、夏までには葉も枯れ、その後は地中で再び春を待つ一連の春植物の総称を スプリング・エフェメラル とよびます。意味は「春の儚いもの」「春の短い命」。ちょっと素敵な和訳でしょ。

地上にその姿を見せてくれるのは、僅か2ヶ月間。その造形美と今日まで絶えることなく生き抜いてきた適応力には本当に驚かされます。
さて、そもそも、なぜ彼らは2ヶ月間しか地上に姿を現さないのか。それは、彼らが林床を終の棲家に選んだからでしょうか。落葉した木々の足元は日差しが十分に入ります。やがて樹木の若葉が広がり、林内が暗くなるまでの期間、光合成を行い、地下に栄養を蓄え、種子を残していったのです。なにしろ、樹木が目を覚ます前に花を付ける必要があった彼らの活動時期は、まだまだ寒い時期で、高く伸びて寒気にさらされることのないよう、そして、何よりまず花に力のほとんどをささげるため、いずれも小さな草本にならざるをえなかったのでしょうか。
気の遠くなるような長い年月を生き抜いてきた彼らの英知を飛騨の自然とともにこれから時折、ご紹介していきたいと思っています。

まさに、百花繚乱。心躍る季節です。

さて、それらの花の中で、春まだ浅い頃顔を出し、早々に花を付け、種子をつけ、夏までには葉も枯れ、その後は地中で再び春を待つ一連の春植物の総称を スプリング・エフェメラル とよびます。意味は「春の儚いもの」「春の短い命」。ちょっと素敵な和訳でしょ。

地上にその姿を見せてくれるのは、僅か2ヶ月間。その造形美と今日まで絶えることなく生き抜いてきた適応力には本当に驚かされます。
さて、そもそも、なぜ彼らは2ヶ月間しか地上に姿を現さないのか。それは、彼らが林床を終の棲家に選んだからでしょうか。落葉した木々の足元は日差しが十分に入ります。やがて樹木の若葉が広がり、林内が暗くなるまでの期間、光合成を行い、地下に栄養を蓄え、種子を残していったのです。なにしろ、樹木が目を覚ます前に花を付ける必要があった彼らの活動時期は、まだまだ寒い時期で、高く伸びて寒気にさらされることのないよう、そして、何よりまず花に力のほとんどをささげるため、いずれも小さな草本にならざるをえなかったのでしょうか。
気の遠くなるような長い年月を生き抜いてきた彼らの英知を飛騨の自然とともにこれから時折、ご紹介していきたいと思っています。

Posted by もりのしぜんがっこう at
◆2009年04月14日14:52
│自然
2009年04月05日
山仕事を体験
うっかりしていたら、もうすっかり暖かくなりましたね
皆さま、お久しぶりです。
今年もレストランではアズマイチゲが咲き始めましたよ。
昨日は育林体験とキャンドルナイトのセミナーを開催しました。
育林体験では、雑木林でコナラの間伐、

切り倒した木にナメコの菌打ちをしました。

この後、周辺の散策、木のカトラリーづくり、と盛りだくさんな一日。
途中で降り出した雨もなんのそので、みなさん日常を離れた森の体験を楽しんで下さったようです。
長かった一日の最後はキャンドルを灯し、温かな灯りの中、食卓を囲みました。

皆さま、お久しぶりです。
今年もレストランではアズマイチゲが咲き始めましたよ。
昨日は育林体験とキャンドルナイトのセミナーを開催しました。
育林体験では、雑木林でコナラの間伐、

切り倒した木にナメコの菌打ちをしました。

この後、周辺の散策、木のカトラリーづくり、と盛りだくさんな一日。
途中で降り出した雨もなんのそので、みなさん日常を離れた森の体験を楽しんで下さったようです。
長かった一日の最後はキャンドルを灯し、温かな灯りの中、食卓を囲みました。
Posted by もりのしぜんがっこう at
◆2009年04月05日17:45
│セミナー